
茨城県石岡市にある割烹ふるさと跡。
『割烹ふるさと』は生板池北岸の森林に寂しく埋もれた飲食店の廃墟である。1972年(昭和47)の航空写真には建物が確認できるが、1969年(昭和44)時点では存在しないことから、この期間に開業されたのではないかとされている。
2000年代前半頃からネット上に廃墟としての情報が出始める。内部を探索された方が収めた写真に1988年(昭和63)のカレンダーがある。これらが閉業時期のヒントとなり得るか。

オーナー、或いは従業員が自殺した(殺害された)ため幽霊が出ると噂されている。
廃墟系心霊スポットによくある話だ。この手の話は根拠が提示されない場合が殆どなので鵜呑みにしないようにしている。
これ以上、心霊に関しての情報は提供出来そうもないから生板池の歴史でも紹介して終わろうかと思う。
生板池について

生板で『まないた』と読むらしい。
1995年(平成7)の朝日新聞には『まないた』という呼び名に『真板』の漢字が当てられ、やがて『なまいた』と訛って呼ばれるようになり漢字も『生板』になったと書かれている。
灌漑用水として造られた人工池だが、堤が築かれた年代は定かになっていない。
生板池には八幡太郎こと源義家に纏わる伝説が残る。
八幡太郎義家が奥州征伐のおり、常陸の国を通ったといわれているので八幡伝説は各所に遺されている。
(一)生板池、市内大字東大橋字香取
(ニ)六万 同右 字六万
生板池は、義家が大橋で軍勢を調べたら六万あったので、その場所を六万と名ずけ(原文ママ)、その六万の兵の水炊をするため池の水を使ったという、それで池の名が生板池と呼ばれるようになり、(後略)
石岡市史 上巻 第8章 伝説より
奥州征伐とは11世紀末に起きた後三年の役のこと。
これは出羽清原氏の内訌から発展した戦いで、源義家が味方した藤原(清原)清衡が勝利を収め奥州藤原氏が誕生することになる。その奥州藤原氏は義家の玄孫(或いは曾孫)である源頼朝によって滅ぼされた。

『水炊をするため池』のほとりで営業していたのね。オーナーは生板池の歴史を知ってここを選んだのかしら?だとしたら言い伝えをセールストークとして使って接客していたのが想像できます。
また八幡太郎の伝説の他に西岸にある祠(現存しているか不明)にまつわる言い伝えも残る。
祠のなかから色白黒髪で隻眼のお姫様が出てきて小さな鉦を鳴らしつつ、けんけん足で祠の周りをまわっているらしい。
このお姫様は幽霊だろうか?それとも神様か?
お姫様の幽霊が出ると噂される心霊スポットを幾つか知っているが、概ね噂の根拠は合戦の敗北に関係していると思う。乱世にのみ込まれた悲劇のヒロイン的な存在だ。ここのお姫様が何に由来しているのか気になるところである。
終わりに

この廃墟は店舗名が判明しているし、それなりに規模の大きい飲食店なので地方紙や雑誌を隈なく調査すれば何かしらの情報が見つかりそうではある。
新しい情報を仕入れたら追記しようと思う。


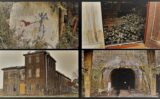


コメント