
鹿島川と塩田川に挟まれた平地に築かれた常広城跡(恒広城)。
現在はその跡地に北鹿島小学校が建っている。
常広の名は1889年(明治22)迄あった常広村が由来。
鹿島鍋島氏の初期居城だったため鹿島古城とも呼ばれる。
戦国時代の終り頃鹿島一帯は有馬と竜造寺が対峙していた。
天正四年(一五七六)竜造寺は鹿島を攻め鹿島地方にあった有馬の城をつぎつぎと攻め落とした。
竜造寺が支配することになった鹿島城には戦に手柄のあった鍋嶋信房がおかれた。
信房はやがて佐賀藩祖となった鍋嶋直茂の兄である。
北鹿島小学校 赤門前 旧鹿島城址由来より
とあるが『元々存在した城に入城したのか、鍋島信房が築城したのか?』詳細は分からない。
常広城の場所

国道444号線にある北加鹿島小学校の信号を曲がった先にある。
かなり狭い道を進むので運転注意!
付近に駐車場が見当たらなかったので、私は広めの道に路上駐車した。
常広城について

孫引きだが、鹿島鍋島氏4代目・鍋島直條が残した『鹿島志』に常広城のことが記されていた。
『本丸は松杉の中に在り、古より之を園と称し楽思と名づく。
池あり林あり園あり圃あり、北隅を松丸と曰ふ。
西方の田畔は是を乙丸と称す。
四面食禄の家連庸す南西には市陌あり、漁村あり、軒を並べ宇を連ね、江を傍うて橋を架す。
さきの所謂横蔵の古戦場なり』とあり、
日本歴史知名大系代四十二巻 佐賀県の地名 常広城跡 488頁より
『横蔵の古戦場』とあるがこれは肥前国の大名・龍造寺隆信が有馬氏の横蔵城を攻め取った戦いのことを指している。横蔵城(横造城)の正確な位置は判明していないが、常広城の程近くにあったとされている。
この戦いの後、沖田畷の戦いで龍造寺隆信は有馬晴信・島津家久に敗れ討ち死にした。
隆信死後、龍造寺政家が跡を継いだが、龍造寺家臣内で力を付けた鍋島直茂が実権を握り大名へと出世、幕末まで続く佐賀藩の礎を築いた。
江戸時代の常広城

1609年(慶長14年)、鍋島勝茂(直茂の嫡男)は弟の忠茂に鹿島2万石を与えた。
ここに鹿島藩が成立する。
常広城は川に挟まれた低地であったため水害に悩まされていた。辛抱強く堤防を築き、城の周りに土手や堀を廻らせたけれども、水害には勝てなった。
1807年(文化4年)、鹿島藩9代目・直彜(なおのり)は常広城の南に位置する高台(高津原)に鹿島城を築き移居、常広城はその役目を終えた。
2009年(平成21)の佐賀新聞に〈歴史検証シンポ、鹿島城の謎に迫る〉という興味深い記事が残っていた。『水害が原因で移動したと伝わるが、大砲による戦いを想定した戦略的な意味があったのではないか?』という内容だ。
利用しているデーターベースサービスは引用禁止なので記事の一部を要約した。

こういう風に様々な見解があって歴史が造られていくのですね。
終わりに

どうやらここ、心霊スポットとして知られているらしい。
心霊サイトを見ると『処刑場があった』とか『洪水で死者が出た』などといったことが書かれている。
処刑場云々は証明の仕様がないので何とも言えないが、城の直近に仕置き場を設置するだろうか?
また、常広城周辺だけではなく、有明海に面する佐賀の平野は昔から水害に悩まされてきた。
ただ洪水を根拠にここだけを曰く付きの場所だとするのに少々の違和感を感じる。


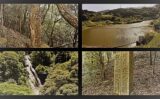


コメント
北鹿島小学校が心霊スポットだと言われ始めたのは20数年前あたりからで当時の小学生が勝手に言い始めた噂話ですよ。
証拠に昔から周辺に住まわれてる方にはその話を知らない方も多いです。
村人Aさん
コメントありがとうございます!
小学生の噂が事の発端だとは…。
無理矢理洪水と関連付けられたりしていますが、ちょっと根拠が乏しすぎるので、なんだかなぁとは思っていました。