
日本の滝百選に選ばれる佐賀県唐津市の観音の滝へ行って来た!
滝川に懸る高さ四五メートル、幅一〇メートルの滝で、観音の滝ともいう。水量豊富で、飛び散る飛沫は鬱蒼たる竹林と左右の奇岩に映える。
日本歴史知名大系代四十二巻 佐賀県の地名 白滝 310頁より
後程詳しく紹介するが、ここは眼病に御利益があるパワースポットとして知られ多くの参拝者が訪れる。
また夏場になると涼しさと癒しを求める観光客で賑わうとの事。
ところがオカルト界隈では観音の滝を曰く付きの場所として扱っている。所謂心霊スポットというやつだ。心霊の根拠はあるのか?
その辺りを探ってみよう。
観音の滝へのアクセス

佐賀大和ICを下りて三瀬方面(右)に進む。
しばらく走ると青看板に唐津・富士・七山方面は左折と出るので、それに従い国道323号線に入る。
30~40分道なりに進むと観音の滝の案内板が見えてくる。駐車場完備。
観音の由来

観音の由来は滝の脇に安置されている生目観音。
観音の滝が眼病に御利益があるとされる理由は戦国時代を生きた『広』という女性にある。
朝鮮出兵の指揮を執るため名護屋城(佐賀県)にやってきた豊臣秀吉は陣中で『広』の世話を受けた。
『広』は大変美しく性格も良かったため秀吉から大層可愛がられ、広沢局とまで呼ばれるようになった。

『広』は或るとき眼の病気を患い七山郷滝川へ訪れ福聚院の観音様にお願いをしたと云う。
この観音様が生目観音だという訳だ。
その分霊が広沢局ゆかりの地・名護屋城山里丸跡に建てられた広沢寺に祀られている。
窪みの水を汲んで祀り、この水で眼を洗うと眼病が治ると説明板に書かれていた。(洗う人は自己責任で)
滝の観音の歴史は古く、大寛2(702)年堂宇が建立され、ご本尊に、聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)が安置されたことが始まりと伝えられています。
聖観世音菩薩が安置された観音堂は眼病平癒にご利益を願った絵馬やお札が奉納されており、古くから眼病平癒にご利益があると伝えられています。
神亀3(727)年に聖武天皇の后・光明皇后がご懐妊中に眼病で苦しんだ際、この地で高僧行基(こうそうぎょうき)と山伏・源成法師(げんせいほうし)が祈祷したところ、眼病が治ったといわれています。眼病平癒のご利益より
広沢局の逸話以前から眼病平癒の御利益があったとする説明もある。
大昔は光明の滝とも呼ばれていたらしい。佐賀県の地名という書籍では白滝と紹介されていた。
観音の滝の歴史を振り返るとパワースポット的な意味合いで大昔から信仰されてきた場所だということが分かる。
では、いつから曰くつきの場所だと言われ始めたのだろうか?
心霊スポットとしての観音の滝

結論から言おう。
観音の滝が心霊スポットとして扱われる原因は多発する水難事故である。
『2008年7月、2010年9月、2017年9月』の新聞記事に観音の滝で発生した死亡事故について書かれていた。3件とも遊泳中に滝壺へ近づき渦に巻き込まれ溺死したという内容だった。
『2010年9月3日・朝日新聞社』の記事によると2006年から今回を含めて4件の水難事故が発生したとある。
短い期間にこれだけの事故が起きているのはちょっと異常だ。
更に過去を遡ればもっと出て来るだろう。

観音の滝は45mの滝であるはずなのに余り迫力を感じない。
滝壺付近の岩場は足場が広く高低差も少ないため歩きやすそうだ。川幅は狭く、透明度が高いため浅く見え、流れもさほど強くなさそうなので(実際はかなり強いと思う)安易な気持ちで水遊びをしてしまうのかもしれない。
滝壺の深さは約4mあるらしい。
見た目以上の滝であり、どれだけ泳ぎに自身があっても滝壺に近づけば引きずり込まれる事必至。飛瀑に巻き込まれ、上も下も判断出来なくなり、やがて溺れ死ぬ。
水難事故が多発しているため観音の滝の遊歩道には柵が設置されていた。私が訪問した時も老夫婦が柵を乗り越えて滝の近くまで歩み寄っていた。
ああいうのが足を滑らせて土左衛門に成り果てる。
自業自得だがそれなりに迷惑なので良い子は近づかないようにしよう。
終わりに

観音大橋から見る観音の滝。
遠くから見ると滝の激しさがはっきり分かる。
霊が事故を起こしたのか、事故が霊を生み出したのかは知らないが、そんなことはどうでもいい。
自然の力を侮るなかれという話であった。


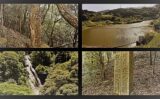


コメント