大分市丹川の赤迫池は灌漑用水(農業)のために造られた人工の溜池である。
歴史は古く、1662年(寛文2)に当時この辺りを治めていた臼杵藩の命を受けた奉行・安野氏が築造したと伝わる。
どういう訳かこの池は心霊スポットとして知られてる。
赤迫池に訪問したので、その風景と共に曰くの由来を考察してみようかと思う。
赤迫池への行きかた
別府方面から国道10号線を進む。(途中で県道21号線に入るが気にせず直進)
大分川を渡り加納西の信号を右折し、大分米良ICを越えた先の分岐を佐賀関、大分スポーツ公園(斜め左)へ。
暫く道なりに進み新田入口の信号の少し先を左に下り、突き当りを臼杵方面へ。
更に突き当りにぶつかるので左折すると右手に赤迫池が現れる。
赤迫池は入口にフェンスがあり車で入れない。
どうやら不法投棄が多いため閉ざされてしまったようである。
赤迫池について

心霊スポットサイトを拝見すると『池を築造する際に人柱を立てた。』から霊が出ると紹介されていることが多い。
霊が訪問者を誘って池に引きずり込むというありがちなお話である。

自殺のスポットとしても有名らしい。
所謂、自殺の名所と呼ばれる場所は、ちょっと調べただけで当たり前のようにそれに関する情報が出てくる。
ここにはそれがないので自殺者があったとしても数える程だと思う。
赤迫池の人柱伝説について

既に冒頭でお伝えしたが、赤迫池の築造記録は残っている。
昭和期の大分市報に書いてある情報なのでほぼ間違いないと思われる。
恐らくは江戸時代の地史書に示されている情報なのだろう。
人柱伝説に対する疑問

奉行が独断で人柱を立てたとは考えにくい。
仮に里人からそのような立案が申し出されたら咎め制止するか藩の上役に相談するだろう。
奉行が藩に報告しなかった、或いは藩が歴史を消したいう可能性もあるかもしれないけれども、そうであるならば人柱伝説は口伝で語り継がれてきたという事になる。
口伝で残っているのであれば、里の民話や研究者の調査情報があってもいいと思うのだが、どうだろうか?
もしかしたら築造中の事故で死亡した人夫を殉職者を人柱としたのかもしれない。
大概そういう場合には慰霊碑や祠が建立されているのだが、池の周囲にはそれらしきものが無かった。
名前の由来

名前の由来の詳細は不詳である。
『赤』を『血』の事だと紹介する者もいるが、わざわざ不吉な名前つける理由があるのだろうか。

『丹』が採れる産地に丹生と名付け、地元の豪族は自らを丹生氏を名乗った。
丹生の地名は日本各地に存在している。
さて、本題。
では何故、『丹』を『赤』にしたのか?
『赤』=『水』説

『赤』には様々な意味がある。
この場合『水』の意味ではないかと私は妄想している。
赤見、赤倉、赤堀、赤城などの地名は『(御神)水が湧き出る場所』や『(御神)水を囲って溜めた場所』の意味があるそうです。
そのまま丹迫池でもいいけれど『縁起がよさそうだから赤にしようか?』といったプラス思考で名付けられたと思いたい。
そして『迫』、これは小さい谷の意。
『丹』が採れた地域の小さい谷に造った灌漑用水の池。
地域の農業の発展を願い、神仏に祈願しようと閼伽由来の『赤』を取り入れたのではなかろうか。
と言ったものの単純に赤土(丹)が採れるから『赤』にしたと考えるのが普通だろう。
実際に『赤』の字を使った地名で上記のような意味を持つ場所が存在するのでここも同様かと思った次第である。
※追記
新たな情報を発見したのでご紹介しよう。
續日本紀曰文武二年九月乙酉豊後國眞朱を献す案するに郷の西北久所村有り地を赤迫と名け多く朱沙を出す葢し此に取る乎
丹生村史 村名及地名の起原より 12頁
丹生 風土記曰。昔時之人。取此山沙該朱沙。因曰丹生郷。
豊後國志より
これを見る限り『赤』に深い意味は無いようだ。
やはり単純に『朱沙(丹生)=赤』が正解なのだろう。
少し残念だ。
二、赤迫溜池奉行の切腹
赤迫溜池は今日から二百六十餘年前寛文二年臼杵藩主の命を受けて奉行安野良治の築造した名池であるが竣工に當り上使の檢分があつた際築堤奉行は手柄顔に此の溜池の水は二百日以上の落水が可能であると申上げた所が稻は田植後幾日間の養水が入用かと反問された。奉行は徒に大なる溜池を築造した事を愧ぢて切腹して御託を申したといふ。
併し此傳説は溜池の貯水量なる事を誇大するための傳説で實は上の褒章に預り安野家は築陂の功により五十石を加増され二百石の祿で明治維新に至つてゐる。
丹生村史 傳説 171頁
溜め池を造った奉行がいたずらに大きい池を造ったことを恥じて切腹したとある。
ところが奉行は溜め池造設が評価され褒章を受け取り、子孫は明治維新まで続いているというオチが付いている。
三、溜池の主蟇蛙
昔佐賀關の大夫(神主)の娘に毛髪は身長より長く全身に鱗の生じたものがあつた。
此の娘は頻りに深い廣い淵を求めて止まなかつた。詮方なく駕籠に乗せて赤迫の溜池につれて來た。
娘は喜んで、身を躍らせて水中に潜り込んだ、暫時にして上り來て曰ふには此の溜池には蟇蛙の主が住んで居るからこゝには棲めないといふので終いに大野川沈堕の瀧に入つて主となつたといふ。
丹生村史 傳説 171~172頁
これは面白い!
鱗の生える娘が淵を求めて赤迫池に赴いたが、ガマガエルの主が住んでいたため沈堕の瀧(大分県豊後大野市)の主になったという伝説。

これを読む感じ、赤迫池は昔から曰くつきの場所として知られていたのかな?
終わりに
今回、赤迫池の名の由来について考察してみたが、巷で囁かれている『赤=血』は少し無理があると思う。
根拠を調べてみると心霊スポットとしての力は弱いと感じた。
『というか本当に心霊スポットなのか?』とすら思う。
もし、赤迫池についての詳細を御存知の方がいらっしゃればご教授願いたいところである。




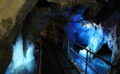
コメント
1662年頃と云えば、島原の乱も終わって、戦いの無い平和な世の中になった後の事。
収穫を増やす目的?で作らたのかな~って推察しました。
農業用あるいは飲料水にも?だったりすると、
偽情報を流してでも、あんまり近づいて欲しくないとか。
400年近く地元に貢献したなら、”吉”ですよね。
上総さん
こんばんは!
“偽情報を流してでも、あんまり近づいて欲しくないとか。”
なるほど~。敢えて不吉な名前にした説ですね!考えてもみませんでした。
名前に由来って興味深いですよね!
地元民です。
赤迫の池に関しましては、田舎ならではといいますか、代々伝承されていますが、地元民の常識としまして
「絶対に近づいてはいけない」
これにつきます。
公にはなっていませんが、昭和から平成までの間でも、実は多くの人が亡くなっています。
○○さんちの○○ちゃんが、引き摺り込まれて溺れたとか、○○さんが自殺したとか
田舎なので、誰が亡くなったのかすぐ広まるんですよね。
近づいてはいけない場所に行って亡くなってしまった…
地元民からすれば、正直言って「馬鹿だな」というのが本音です。
それぐらいの場所なのです。
昔、丹生地区が飢饉に襲われたところ、当時の人々が行った対策が人工池を作り、備える事でした。
池を作ったのはいいものの当時の人々は、再び飢饉に襲われた時、この池の水までも干上がってしまう事を恐れました。
そこで行われたのが人柱を立てる、という事だったのです。何人かまでは伝承されておりませんが、丹生地区に昔から住んでいる人なら必ず知っている事実です。
散策されたそうですが、その人柱の人達を祀っている祠はあります。
心霊スポットとしてヤバイのは池よりも、この祠と言われています。
この祠を代々管理している家があるそうすが、知っている人はほとんどいません。
又、丹川地区についても伝承されています。池に赤を使うのは、池が危険である事を認識させるためです。
地区が丹なのは、人が住むにあたって血を連想させるわけにはいかなかったからです。
表向きとして、いちちさんの仰る意味も伝わっていますが、実際は昔、争った人々の血によって川が赤く染まった事に由来しているのは、確かに一部の人しか知らないですしね。
そういう歴史を地元で伝えつつも、マイナスなイメージは避けたい事から「丹川」なのです。
赤とすることで、赤迫の池は現在もなお危険な場所として認識されていますが、丹とした丹川はたくさんの人が、平和に暮らしています。
実のところ、丹川地区においても、とある集落は不幸事が多い場所もあり、これこそ地元ならではの怪奇だと思ってます…
新居者が来ても、その家族の誰かが急死したりだとか。見渡しがいいのに事故が多いとか。
でも、誰もそれを土地が悪いからだとは言いません。あぁ、やっぱりとしか思いません。
いちいちそんな事を言っていては、日本全国どこにでも死者はいますし、キリがないからです。
でも、伝承していく事は大切だと思います。
全国には様々な心霊スポットと言われる場所があり、ネットでは様々な話が飛び交っていますが、私は、その土地に代々伝承されてきた事を今後も子孫に伝えていく事が大切だと思っております。
黒鋼 さま
コメントありがとうございます。
『續日本紀曰文武二年九月乙酉豊後國眞朱を献す案するに郷の西北久所村有り地を赤迫と名け多く朱沙を出す葢し此に取る乎
丹生村史 村名及地名の起原 12頁より』
『丹生 風土記曰。昔時之人。取此山沙該朱沙。因曰丹生郷。
豊後國志より』
後日、詳しく調べてみたところ以上の情報が見つかりました。
文武という元号はありませんが、文武天皇の時代でしたら8世紀前期でしょう。
私は『赤=水』じゃないかと推察しました。しかし歴史的に見ると『朱沙→赤/丹生』が正解のようです。
續日本紀と豊後國志は信憑性のある史料だと思いますのでほぼ間違いでしょう。
『ほこら』や『多くの方が亡くなっている』に関しましては私は証拠が出せませんので何も言えません。
人柱の事実は確認できませんでしたが、奉行切腹の噂や池の主が蟇蛙だという伝説が残っているようです。
今回、調べたことを追記致します。
貴重な情報ありがとうございました!
こんにちは丹生に住む佐藤と申します。
昔話調に丹生の伝説を作りましたので案内します。
①丹生暮らし365を検索
②丹生の伝説
一回から十回あります。
佐藤洋作 さま
サイトを確認致しました。
後日、youtube(大分市丹生伝説)を拝見し掲示板にコメント致します。