 熊本県
熊本県 重要文化財の霊台橋の歴史【熊本】
弘化2年、惣庄屋に就任した篠原善兵衛が石橋の架橋を計画します。施工者は大工棟梁の伴七、種山村の石工である卯助、その兄弟の宇市、丈八。そして地元の民衆です。工事は弘化3年に開始され6~7ヶ月後、翌年の弘化4年に落成、渡初が行われました。梅雨や台風を避けるためかなり急ピッチで作業が行われたそうです。
 熊本県
熊本県  宮崎県
宮崎県  佐賀県
佐賀県  宮崎県
宮崎県  宮崎県
宮崎県  宮崎県
宮崎県  福岡県
福岡県  福岡県
福岡県  福岡県
福岡県  大分県
大分県  大分県
大分県  大分県
大分県  大分県
大分県  大分県
大分県  山口県
山口県 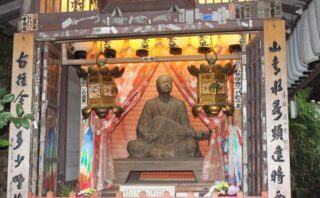 山口県
山口県